前回は「正義」についてプラトンを中心に考えました。今回は、二十世紀最大の政治哲学者と言っても過言ではないジョン・ロールズの思想について「学校」のメタファーを使って考えていきたいと思います。プラトンは「正義」が何かについて非常に明快な示唆を与えました。でも、「どうやったら正義を実現できるのか?」については、複雑な現代に生きる私たちが具体的にすぐ行動を起こせるような、誰にでもわかるような方法(How)を指し示すことはありませんでした。
だって、さまざまな欲求を持ち、さまざまな個性・技能・卓越を持つわたしたちが全て幸福になれる世界なんてどうやったら実現するのでしょう?私たちは「家族」内や「職場」内ですら、お互いの価値を認め、いつもハッピーに暮らせるとは限りません。どんなに近しい人であっても、全く同じ主義主張を持つことはありえません。さまざまな考え方を持つ私たちが調和し、一緒に生きていくために、どうしていかなければならないのでしょう。ロールズは、そんなことを『正義論』で考えました。[i]
たとえば、「職員室」ではなにが起きているでしょうか。教師は、さまざまな「教育」に関わる信念を持っていて、それはバラバラです。ある先生は、「学ぶ」とは「真理を学ぶこと」「真理をよく知る人から教えてもらうこと」だと考えるかもしれません。そうするとその人は「古典」をベースにレクチャーをする、という授業形態を持つかもしれません。その場合、永続主義という信念を持っていることが考えられます。逆に「学ぶ」とは、「さまざまな経験によって自ら意味合いを見出していくものだ」と考えている人は、「何かを教える」前に「子どもたちには、なんらかの経験をしてもらう」ように促すかもしれません。その場合、その教師は「進歩主義」の考え方を持っていることが考えられます。先生の授業実践と、日々の教える態度(Teaching Behavior)は、教師個々人の「学び」に関する隠れた信念が滲み出るように現れてくるものなのです。そして、それは当然にして多様なものになります。以下の表は、さまざまな主義における「考え」の違いを表したものです。

『探究する学びをつくる』拙書 p57
学校のような小さな単位であったとしても、教師一人ひとりの「学ぶ」に関する信念はバラバラです。「探究学習」をしたいと思っても、それに同意できない先輩の先生が多くて進まず、「あの先生とは全く価値観が合わない」とため息をついてしまう、ということは多くの先生が経験しているのではないでしょうか。
「漢字は書き順通り学ぶべき」「学校校則は将来社会でスムーズに適応するために必要」「良い一斉授業のほうが学び合いより効果的」という先生がいるかと思えば、「いやいや学校校則は民主的に生徒たちが決めて良い」「生徒はアクティブに学ばないと知識が身につかない」などさまざまな意見が飛び交います。
つまり、私たちは、自分たちではそれほど意識していない部分で、「これが善い学びだ」という強い信念を持っているのです。ロールズはこれを、「善の構想―conception of the good」 といいます。[ii]そして、それは「信念」であるがゆえに、なかなか譲ることもできないし、受け入れることができません。そんな中、学校としてみんな同じ方向を向くのは面倒くさい。だから、自分の好きな実践を自分の教室だけでできることをこっそりやればいいじゃないか、となりがちです。
ただ、現実社会では、自分の好きなことを自分の教室だけでやるように生きていればいいのかというと、そうは問屋が卸しません。子どもたちは将来、さまざまな主義主張のある人たちが集まる中、意見の違うメンバーと一緒に何かを創り上げる必要に迫られるかもしれません。そうだとしたら、教師もその経験を身をもってしなければならないかもしれません。
なぜそんな面倒臭いことをするのか。それは、「主義主張、信念が違うそれぞれの構成員が協働することによってこそ、一人ではできなかった何かを生み出すことができるのではないか」という仮説があるからです。そして、そこにこそ「学校の意味」を見出すためのヒントがあるし、そこにロールズがとても重要な示唆を与えてくれているのです。
【ロールズってどんな人?】
ところで、ロールズといえば、「無知のベール」がよく知られています。つまり、社会的公正(fairness[iii])を考える場合に、思考実験として、性別や、人種など自分の社会的立場、どんな能力を持ち、どんな健康状態かについてベールをかぶってわからなくしてしまった上で、そのベールが取っ払われて、自分がどの立場にあっても大丈夫と思えるような判断をしよう、という考えです。たとえば、もしベールをはいだ時に、自分が歩くこともできず、目も見えない人だったとしたらどうでしょう?今の政策に合意できるでしょうか。そして、こうした想像力は教室の中でも必要不可欠ではないでしょうか。そして、こんなすごいアイディアを考えたロールズは、どんな人だったのでしょう?
神島裕子『正義とは何か〜現代政治哲学の6つの視点』によると、ロールズは、父親は弁護士、母親は女性有権者の会の会長もつとめたこともある、経済的に裕福で、社会正義に関心を寄せる家庭に生まれました。5人兄弟の2人目ですが、7歳の時にジフテリアに罹り、ロールズ経由で感染した弟を一人喪います。8歳の時には、肺炎に罹り、この時もロールズから感染した別の弟を喪ったそうです。プリンストン大学に進学しましたが、吃音があったこともあり、父親や兄弟と同じ弁護士の道は選ばず、哲学を専攻しました。
時代は第二次大戦のさなか。ロールズは卒業後すぐ陸軍に入隊し、歩兵連隊の一員としてフィリピンのレイテ島やルソン島で日本軍と戦います。1945年8月の終戦時には、山下奉文大将をジャングルから連れ出す任務に志願して参加し、9月にはGHQの一員として来日し、原子爆弾投下後の広島を列車で通過するなど、日本とも縁のある人です。そして、第二次大戦後、アメリカでまだまだ実態としては激しい人種差別がのこっていました。1968年にはキング牧師が暗殺されます。
そのような中、1971年、ロールズは50歳の時に『正義論』を発表、この本で、社会の全ての人々の自由と権利のために「公正としての正義(Justice as Fairness)」と称される正義を構想しました。『正義論』はまさに、当時停滞していた政治哲学の領域に大旋風を巻き起こします。各大学でこの本が授業で取り上げられるだけではなく、関連論文や著作が次々に発表され、研究会やシンポジウムが開催され、アカデミズムにおいて、いわゆる「ロールズ産業」が形成されていったのです。この思想的立場は「リベラリズム」と呼ばれ、福祉国家の哲学的基礎としての地位を確立します。(K,20-23)
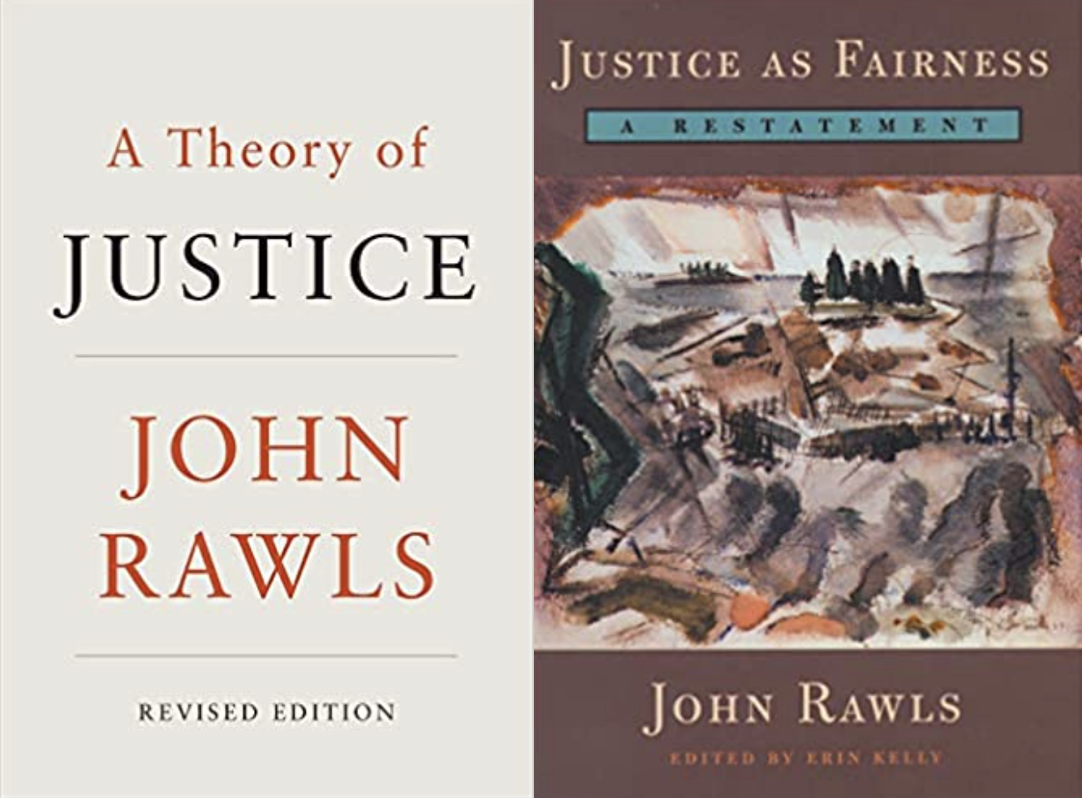
【社会的協働が正義のベース】
先に述べたように、私たちは、ささいなことでも合意することがとても難しい。「学ぶ」ということひとつとっても、みなさまざまな信念があり、ぶつかり、みんなプロジェクトを一緒に進めるのに苦労します。同様に世の中で、「善」といっても、さまざまに多様な「善」の構想をみんなもっているわけですが、どうやったら、私たちはフェア(公正)に合意していけるのでしょう?
ロールズは、『公正としての正義再説』の第一部において、政治哲学の役割を4つ述べていますが、この内容は学校組織にもほぼそのままあてはまります。
1)さまざまな信念を持つ私たちがどうやったら合意をとりうるのか
深刻に論争されている諸問題に焦点を合わせ、政治的・道徳的な合意のなんらかの潜在的な基礎を探り出せないかどうかを見定める(KS,3)
2)わたしたちはどうやったら国家の目的や目標をみいだせるのか
制度の基本的な目的や目標を、個人あるいは家族や結社の構成員の目的や目標としてではなく、(略)国家のそれとして考える (KS, 4)
3)多元的な私たちは和解(宥和)し、本当に自由で平等になれるのか
ヘーゲルが『法の哲学』で強調した宥和という役割(KS,6)われわれは、政治社会を(略)協働の公正なシステムとしてみることによって、(穏当な多元性の事実の中で)この問題(宥和)を論じる。
4)私たちは、最高の社会の仕組みを現実の中でどこまで実現できるか
われわれは政治哲学を、現実主義的にユートピア的なもの(略)の限界を徹底的に調査することとみなす
これらの役割を学校の文脈で言い換えると、たとえば1)については、先に述べた通り、「学ぶ」ひとつとっても、安易に合意できない私たちがどのように合意をとりうるのだろうか、ということ。2)3)については、ロールズが「政治社会は結社ではない(KS,7)」と言っているところが重要です。つまり、会社であれば、その会社のミッションや期待する能力に合致しなければ、採用しなければいいし、会社が嫌なら辞めればいいでしょう。でも、国はそんなわけにはいきません。国のスタイルとあなたが合わないから出ていってください、死んでくださいとは言えません。でもこの状況は(特に公立の)学校の状況と酷似しています。学校の基準を決め、合わない子を排除してはならないのです。そのような中で、私たちはどうやったら、納得解を見出せるのでしょうか。4)も面白いです。論理的に完璧なものを目指せと言っているのではなく、不完全でよいから適度に正義に適い、逆に短命に終わらない民主的政体を模索していきます。
公教育は、目が見えない、歩けない、深刻な病気に苦しんでいる子どもも受け入れます。自閉症や、発達障害、小さな頃から虐待を受けて、精神的な病気を抱えてしまった子もいます。記憶力がよく、テストで高い点数を容易に取れる子もいれば、どんなに頑張っても良い点数を取れない子もいます。絵を描くのが上手な子がいれば、歌を歌うのが上手な子がいる。良い点数がとれなくても、人に優しく、思いやりを持った子もいれば、(さまざまな理由で)人を傷つけることをなんとも思わない子もいます。
それに加えて、先生たちの信念もさまざまです。私たちはLearning Creator’s Lab(LCL)という年間の教育者研修を実施していますが、そこでは、最初にさまざまな教育手法を学び、自分に一番フィットする「学び」を感じ取っていきます。その上で、みんなの「学び観」「信念」が違うということを認め合った段階で、チームを組んで協働プロジェクトを実施するのです。当然例年「チームではなく、一人でやりたい」、もしくは「好きな人とだけやりたい」というリクエストが必ず出ます(笑)。もちろん、一人でやったほうが進む作業というものもあるし、私も個人作業が大好きです。
でも、それでもなおロールズは、協働の冒険的な企て(cooperative venture for mutual advantage)が社会にとって必要不可欠だと言います(KS,40)。もちろん利害が一致せず、衝突のある世界。でも、一人がバラバラにいるよりも、社会的協働によってより良い生活ができるはず。” Cooperative venture(コーポラティブベンチャー)” という言葉の響きの中に、決して楽ではないけど、意味あるもの、のニュアンスが伝わるでしょうか。「あの子は歌が上手くないから、合唱チームに入れたくない」ではないのです。まさに「早く行きたければ、ひとりで行け。遠くまで行きたければ、みんなで行け。」なのです。(LCL卒業生がCooperative Ventureの大変さと意味を語ってくれていますので、よかったらこちらを。)
ロールズは正義の構想において最も基礎的な観念は世代を超える「公正な社会的協働システム」(KS,10, 『正義論』第一節4頁)だとします。つまり「公正」のために全構成員にメリットのある互恵性(KS,12)を支えるルールが手続きとして成り立たなければなりません。
そのルール上で、仮に全構成員の間で包括的な合意ができなかったとしても、正義の政治的構想には合意できる「秩序だった社会(well-ordered society)」が成立するとしています(KS,17)。教室のメタファーとして考えると、「学ぶ」について「本質主義」や「進歩主義」、「実存主義」などみんな違う主義を持っており、それで究極の合意ということはあり得ないのだけど、学校組織の中で、正義として合意できる「構想」を認識し、受け入れることは可能だ、というイメージでしょうか。
ロールズも言っているように、それは「明らかに相当程度理想化したもの」かもしれませんが、その合意こそが社会のスタートです。そして、それを基本構造(basic structure)が支えます。基本構造は、「基本的な権利と義務を分配し、社会的協働が生み出した相対的利益の分割を決定する方式」(KS,41)であり、現実社会でいうと、法制度、政治制度、市場制度、所有制度、家族制度といった、社会的な諸制度の集合体のことですが(KS,33)このあと述べる正義の二原理に従って編成されると、これら諸制度を通じて、平等な基本的諸自由と社会的に最低限の生活が各人に保証されることになります。(KS,41)このように、ロールズの正義はそもそも社会的協働の正義を目指しているのです。
【無知のベールと正義の二原理】
では、どのようにしたら、こうした秩序だった社会、そしてそれを支える基本構造を社会的な協働という文脈の中で合意できるのでしょうか。
その時にロールズがいうのは、(なんらかの社会契約が結ばれる以前の)原初状態(Original Position)に私たちが戻って判断し、OKを言えることが必要だと言います。原初状態の人とは、ベールがかかっていて、私たちの社会的な立場や、財産、能力、健康などについて知りません。[iv]なので、もしベールが取られた時に、「わたしは、すごくお金がなくて路頭に迷わなければならないような状態であり、且つ肢体不自由であるかもしれない。それでも私はこの社会にOKを出せるか?」と考えるわけです。

Veil of Ignorance https://haam.org/tag/veil-of-ignorance/
教育にあてはめてみます。もし学校が「本質主義」一色になってしまったとしたら、どうでしょう?たとえば、大きな教室で一時間座って、教師の講義を聞き続けなければならない、となった時、もし自分がその古典に対する知識も理解力もなく、じっと座っていることが苦痛なタイプだったら、その主義に合意するでしょうか。要は、「無知のベール」は、そのような想像力を私たちに働かせるための工夫みたいなものになります。
そうやって「原初状態」のわたしたちが提示した原理を、さらに「道徳的能力[v]」を使いながら、調整していくわけです。たとえば、「学び」において、自分が「進歩主義」の信念をもっていたとすると、「本質主義」の考え方の人たちのことをどのように認め(承認)し、且つ和解(宥和)できるかというフェーズに入っていきます。それは、ある程度自分の主義を譲らずとも、相手の主義を受け入れる、というレベルから、さまざまな「主義」を外観した上で、一つ上のレイヤーで合意できるような構想を考えることも含まれます。さらにいうと、その構想がみんなに認められなければなりません。このプロセスをロールズは「反省的均衡(reflective equilibrium[vi])」と言いました。私たちは、違った主義主張があったとしても、必ず重なり合う部分があります。その「重なり合うコンセンサス」を大事にしながら、均衡点を見出していくわけです。
正義の二原理は以下のとおりとなっています。(KS,83)
第一原理
各人は、平等な基本的諸自由からなる十分適切な枠組みへの同一の侵すことのできない請求権をもっており、しかも、その枠組みは諸自由からなる全員にとって同一の枠組みと両立するものである。
第二原理
社会的・経済的不平等は、次の二条件を充さなければならない。
a)社会的・経済的不平等が機会の公正な平等という条件のもとで、全員に開かれた職務と地位に伴うものであるということ。
b)社会的・経済的不平等が社会のなかで最も不利な状況にある構成員にとって最大の利益になるということ(格差原理)
※第一原理は第二原理に優先する。第二原理のうちa)はb)に優先する。
よく言われるのが第二原理のb)の格差原理で、「もっとも不遇な人びとの最大の便益に資するように」ですが、まさにこれを容易にするのが、「無知のベール」となります。
また、第二原理のa)「公正な機会均等の原理(Fair equality of opportunity)」については、ロールズも「難解で完全に明快な概念ではない(KS,84)」というように難しいのですが、自分の出身の社会階層(性別、人種、経済格差などを含む)にかかわらず、(才能とやる気があれば)同一成功の見込みが与えられてしかるべきだ、という考え方になります。
ここで第一原理に戻ります。第一原理の「平等な基本的諸自由」には政治的な自由(投票権など)、言論および集会・結社の自由、良心の自由、個人的財産を保有する自由、恣意的な逮捕や押収からの自由を指します。(K,35)第一原理は、具体的には明文化されていようが、暗黙知であろうが、憲法のようなものになります。(K,36)
たとえば、クラスの全員の自由を守ろうと思ったら、ある子の自由を守るためには他の子の自由を制限する必要が出てきます。でも、そこに自由の承認だけではなく、お互いに修正や妥協、取り下げなどの痛みも伴う関係性の中での宥和が必要です。さらに「平等な基本的諸自由からなる十分適切な枠組み」(つまり憲法的なもの)に対し、もし不服であれば(お互いの自由を認め合う中で)妥当な請求の権利を持つことができる、というのもとても重要なポイントです。
そして、この二原理が具体的にどのように運用されていくかというと、以下の4段階で適用されます。(KS,91)
1)無知のヴェールで当事者が正義原理を採択します
2)基本的権利と自由を保障する憲法制定会議をひらきます(第一原理)
3)正義の諸原理が要求する法律を定めます(第二原理)
4)行政官における適用と、司法官による解釈がなされます。
つまり、第一原理に従って、平等な基本的諸自由が分配され、第二原理によって基本財が各人に分配されます。ここで私がとてもいいな、と思うのは「分配的正義」と言った場合、通常私たちは税金や福祉といった所得の再分配のことを考えてしまいますが、「社会的協働の産物」としての基本的諸自由の分配であるというロールズの考え方です。(K41) つまり自由は、決まった量しかなくてゼロサムの奪い合いなのではなく、社会的協働によって、(アーレントの言葉を借りていうと)自由を創設していけるということだと理解しています。たとえば、理不尽な校則に対するプロジェクトを協働で立ち上げようとする営みの中に「自由」が創設されます。そういった意味でプロジェクト(活動)によって「自由」を生み出せるという感度を私たち教育者は常に持っていたいと思っています。
そもそも日本国憲法は、14条で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とされていますが、そのことを私たちはどれだけ実感できているでしょうか。もし実感できていないのであれば、自由は私たちが創設していかなければならないのではないでしょうか。
ロールズは、多様な私たちが「善」について合意することの難しさを心底わかっていた人だと感じます。そして、そうでありながらも、協働によって生まれる基本的諸自由のことをとても理解し、信頼していたのではないでしょうか。
またまた長いブログとなってしまいました。次回はサンデルについて。
※ほかの哲学関連のブログはこちらから。https://kotaenonai.org/tag/philosophy/
<参考図書>
『正義論 改訂版』ジョン・ロールズ 紀伊国屋書店 (S)
『公正としての正義再説』ジョン・ロールズ, エリン・ケリー編 岩波現代文庫(KS)
『正義とは何か〜現代政治哲学の6つの視点』神島裕子 中公新書 (K)
『純粋理性批判』カント 中山元訳 光文社古典新訳文庫
『実践理性批判』カント 中山元訳 光文社古典新訳文庫
『啓蒙とは何か』カント 篠田英雄訳 岩波文庫
[i] ロールズは『正義論 改訂版』の序文において、<公正としての正義>の中心理念および達成目標とは、立憲デモクラシーの哲学的な擁護論の“ひとつ”を構想しようとするところにある、そしてそれが完璧な説得力を備えていないとしても、この構想が広範な人々の思慮深い政治的意見に照らしても妥当(reasonable)かつ有効であり、したがってデモクラシーの伝統が共有する核心の本質的な部分を表現したものであってほしいーそう私は希望する、としています。
[ii] 『公正としての正義』では四部以降で、さまざまな「善の構想」つまりみなが「善」だと感じる多様な政治のありかたについて論じて行きます。実際に私たちは、マルキシズム、功利主義、リバタリアニズム、リベラリズムやコミュニタリアニズムなどなど、さまざまな政治的信念を見えないところで持っています。ここでは、教育者が感じる「善い学び」の構想(隠れた信念)をメタファーとして扱います。
[iii] ロールズの本で「公正」といった場合、Fairnessを指し、ハイテックハイでいうところのEquityとすこし違う語感を持ちます。Fairnessといった場合に、「少しずつ譲り合いながらも、合意する」という語感があります。私がFairnessを実感した経験は、20年前に父の会社が倒産し、その直後に父が亡くなった時、法律によって家族がその債務を引き継がなくて良いと知った時のことです。「フェアな法」に助けられた、と心底思いました。論理で考えると、貸した側から見れば、債務不履行なわけだから本来納得いかないかもしれません。でも、法律が、正義の原理に適っているということに助けられた、まさにJustice as Fairness(公正としての正義)の経験でした。ちなみに拙書『探究する学びをつくる』で紹介したHigh Tech HighにおけるEquityの訳としては「公正」を選びました。(SEL(Social Emotional Learning)を日本に紹介された小泉令三先生がeducational equityを教育的公正と訳出されていたため)。
[iv] 一方で、人間社会に関する一般的な事実は知っていて、基本財だけは欲します。基本財については、議論があり、ロールズは、オリジナルの『正義論』から修正を加えています。基本財は、もともと「合理的な人々が他にどんなものを望んでいようとも必ず欲しがるもの」と定義しましたが、ロールズ自身が『正義論改訂』の序文(S,xiv)にあるように、ハートの批判を受けて、基本財の定義に「深刻な弱点」があるとし、「自由かつ平等な市民としての社会構成員としてのニーズ(簡略化)」であり、単純な欲求を満たすもの(効用)とは対局にあるもの、としています。さらに、1998年ノーベル経済学受賞者のアマルティア・センは、ロールズの「基本財」について、平等であるべきは基本財ではなく、「基本的ケイパビリティ」であるという論陣をはりました(K56) センの持ち出したケイパビリティ(潜在能力)とは、ある人が何かを行ったり、何かになったりするための、実質的な自由のこと。(財(達成する手段)や機能(達成された状態)に依存する)ハイテックハイの「公正」の定義には、センのケイパビリティアプローチの考え方が入っているように個人的には思っています。
[v] ロールズは、『正義論』を書いた後、ロールズの研究関心は道徳心理学に向かっていたようで、ピアジェの後継者である、ローレンス・コールバーグを参考にして考察していました。コールバーグは子どもを対象にした実験を通じて、道徳性の発達は年齢の上昇とともに、6段階に上昇するという説を唱えていました。(KS,30)結局『正義論』の発表後、正義原理にロールズ産業の興味が集中して、思うように進まなかったようですが、カントのいうような最高次の「原理の道徳性」をロールズは倫理学として前提においていることもあり、この分野の研究が進んでいたら、どうなったのだろうと、想像します。
[vi] ロールズが理論として用いたのは、社会契約説(達成目標として、ロック、ルソー、カントに代表されるような社会契約の伝統的な理論を一般化し、抽象化の程度を高める (S,序文xxi))と「反照的均衡 reflective equilibrium(公正としての正義再説では反省的均衡)」と称される倫理学的方法。正義論の民主的な正しさを担保する上で、「反照的均衡」は大事なポイントになります。ロールズは、「秩序だった社会」の構想のためには、「自由で平等な人格」が必要で、そこには「道徳的能力」がなければならない、とします。反照的均衡では、原初状態の私たちが提示した原理と、私たちの道徳的判断が整合しない場合は、いったりきたりしなければならないことを指します。ロールズが想定している道徳判断とは、カントのいう最高次の「原理の道徳性」に達したカント的な道徳的人格を持つ人による道徳的判断だと言います。カントは、<全員が従ったとしても望ましい世界となるルールに従え、そのようなルールのみが道徳法則だ(君の格律が普遍的法則となる)>という定言命法によって引き出される「誰もがしたがうべき法」に従っている時に法的正義の状態にあるとされます。(K,53-4)
<私たちについて>
こたえのない学校HP
こたえのない学校ブログ
Learning Creator’s Lab – こたえのない学校の教育者向けプログラム
こちらをクリック→Learning Creators Lab
Facebook ページ →https://www.facebook.com/kotaenonai.org
